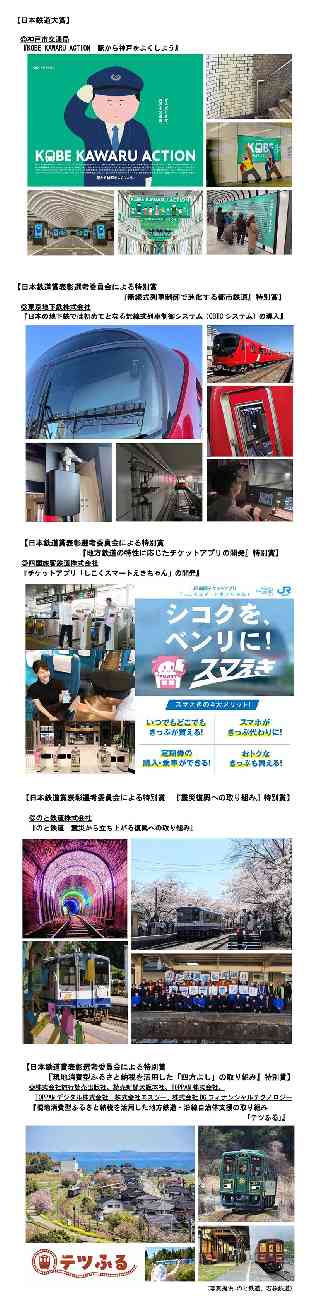| ひろやす/伊藤(vnnc8158) 2025-09-13 03:20:44 |
[出典:国土交通省ホームページ] 国土交通省 Press Release Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism 令和7年9月12日 鉄 道 局 鉄道サービス政策室 第24回「日本鉄道賞」の受賞者が決定しました! 【日本鉄道大賞】 ○神戸市交通局 『KOBE KAWARU ACTION 駅から神戸をよくしよう』 【日本鉄道賞表彰選考委員会による特別賞】 ○東京地下鉄株式会社 『日本の地下鉄では初めてとなる無線式列車制御システム(CBTCシステム)の導入』 ○四国旅客鉄道株式会社 『チケットアプリ「しこくスマートえきちゃん」の開発』 ○のと鉄道株式会社 『のと鉄道 震災から立ち上がる復興への取り組み』 ○株式会社旅行読売出版社、読売新聞大阪本社、TOPPAN株式会社、TOPPANデジタル株式会社、株式会社エスツー、株式会社DGフィナンシャルテクノロジー 『現地消費型ふるさと納税を活用した地方鉄道・沿線自治体支援の取り組み 「テツふる」』 「日本鉄道賞」は、「鉄道の日」創設の趣旨である鉄道に対する国民の理解と関心を深め、国民の強力な支持を得るとともに、鉄道の一層の発展を期することを目的としており、鉄道に関する優れた取り組みに対して表彰するものです。 【選考の方法】 日本鉄道賞表彰選考委員会において、全応募案件(計32件)の評価により、ヒアリング対象案件(計11件)を選出。選出された11件について、応募者よりオンラインでヒアリングを行い、改めて各委員が評価・議論の上、選考、受賞者が決定されました。選考理由については別紙をご参照下さい。 【日本鉄道賞表彰選考委員会委員】(50音順 敬称略) 委員長 加 藤 浩 徳 (東京大学大学院工学系研究科教授) 小 倉 沙 耶 (一般社団法人交通環境整備ネットワーク審議役) 須 田 昌 弥 (青山学院大学経済学部教授) 長 根 広 和 (日本鉄道写真作家協会会長) 藤 井 聡 太 (公益社団法人日本将棋連盟 / 棋士) 藤 田 大 介 (日本テレビ放送網株式会社 / アナウンサー) 道 辻 洋 平 (茨城大学学術研究院応用理工学野教授) 山 口 昌 彦 (株式会社交通新聞社 月刊「旅の手帖」編集長) 五十嵐 徹人 (国土交通省鉄道局長) (別紙) 【日本鉄道大賞】 ◎神戸市交通局 『KOBE KAWARU ACTION 駅から神戸をよくしよう』 (選考理由) 多くの地域が抱える人口減少は、神戸市にとっても大問題。そんななか、鉄道はなにができるのでしょう? 神戸市交通局のプロジェクトの内容は、びっくりするものでした。「まずは駅を掃除しよう」。そうそう、誰だって自分の家に人を呼びたいなら、部屋をきれいにします。とくに駅は地域の玄関。いつもの業務を終えた終電後、みんなで壁を、階段を、床をごしごし。驚くほどにピカピカに。それが済んだら今度はトイレをごしごし。おいしくておしゃれな店も人を呼ぶかもしれませんが、みんなが使う駅のトイレはしゃれた店より先に大事なこと。ちゃんと心地よく使ってもらえる場所に。 「社会や地域の課題」というとつい大仰に考えてしまいますが、できること、実はいっぱいあるんじゃないか。神戸市交通局はそこに気づき、そして私たちに気づかせてくれました。スタートはお金を動かすのではなく、一人一人が手を動かすこと。等身大でシンプルだからこそ、強く地域の心に響いたメッセージ。「駅のヘンシンは、神戸の未来のヘンシンにつながっていく」。地域と鉄道の素敵なストーリーを残してくれた神戸市交通局へ、ここに日本鉄道大賞を授与します。 【日本鉄道賞表彰選考委員会による特別賞 『無線式列車制御で進化する都市鉄道』特別賞】 ◎東京地下鉄株式会社 『日本の地下鉄では初めてとなる無線式列車制御システム(CBTCシステム)の導入』 (選考理由) 東京メトロは、日本の地下鉄として初めて無線式列車制御システム(CBTC)を導入し、2024年12月より丸ノ内線全線での使用を開始しました。地下鉄は、地上鉄道に比べて高密度運行や複雑な線形、限られた空間での地震対策など、運行と設備の両面で厳しい条件に置かれており、新技術の導入は容易ではありません。今回導入されたCBTCは、地上と車上が常時無線通信で連携し、高精度な列車位置の把握と柔軟な運転整理を実現しました。これにより遅延回復性能が大幅に向上し、ラッシュ時でも安定した運行が可能となりました。加えて、信号機や軌道回路などの地上設備を削減することで、保守の効率化と設備故障リスクの低減も達成しています。 また、将来の相互直通運転拡大を見据えて複数の事業者と協力し、共通仕様を策定しました。異なる路線間でも同一の車上装置で運行できる環境を整えました。 これらの取り組みは、安全性・効率性・信頼性を高い水準で両立させ、都市鉄道の発展に向けた新たな一歩となるものであり、その先駆性と実用性は高く評価されます。ここに、『無線式列車制御で進化する都市鉄道』特別賞を授与します。 【日本鉄道賞表彰選考委員会による特別賞 『地方鉄道の特性に応じたチケットアプリの開発』特別賞】 ◎四国旅客鉄道株式会社 『チケットアプリ「しこくスマートえきちゃん」の開発』 (選考理由) 都市圏ではない地方鉄道は経営、運営上などの様々な課題が表面化しています。都市圏ではあたりまえのように普及している交通系ICカード体系を、そのまま地方鉄道でも展開しようというのは、導入、維持コスト面などからも難しい状況ということは容易に想像ができます。 スマートフォンを利用したチケットアプリは多くの交通事業者が導入していますが、定期券や回数券などに限られているものが多い現状です。駅の無人化や普通列車のワンマン化を進めるJR四国の現状に即して、片道乗車券や自由席特急券を、利用者が任意の駅間で発券できることは特筆すべきことです。また、利用者の視認性はもちろん、不正防止を意識した係員が見やすい画面デザインは秀逸であり、自動改札でのQRコード利用にも対応しています。今後JR四国エリアを越えた鉄道会社間での片道乗車券などの発券に進化していただきたいと、ユーザー目線としても強く感じます。 地方鉄道においてJR四国同様の課題は山積していることと思われます。今後このスマえきチケットアプリのシステムが、交通事業者間での共通システムとして進化し、さらなる利便性の向上につながることを祈念して、ここに『地方鉄道の特性に応じたチケットアプリの開発』特別賞を授与します。 【日本鉄道賞表彰選考委員会による特別賞 『震災復興への取り組み』特別賞】 ◎のと鉄道株式会社 『のと鉄道 震災から立ち上がる復興への取り組み』 (選考理由) 2024年1月1日に発生した能登半島地震は、当地の人々に甚大な被害をもたらしました。能登半島中部の七尾〜穴水間33.1kmを走る「のと鉄道」もその例外ではなく、全線で約50か所に及ぶ甚大な被害を受けました。にもかかわらず、地域の復興、そして「何としても学校の新学期に間に合わせたい」という一念で、震災後3ヶ月余りで全線運行再開を果たしました。そして運行再開後は、子どもたちをはじめとする地域住民に元気と笑顔を届ける事業を行う一方、震災の記憶を風化させないための「震災語り部列車」をはじめ、地域との連携のもと鉄道の魅力を高め、より多くの人々に能登半島を訪れてもらうための活動を続けています。 1つ1つは地道な活動も多いのですが、全体を通してみたとき「地域の人々のために」そして「地域の人々と共に」ありたいという強い思いが伝わってきます。そのような一連の取り組みの継続に敬意を表し、未だ道半ばの復興が進んでいくことを祈りつつ、ここに『震災復興への取り組み』特別賞を授与します。 【日本鉄道賞表彰選考委員会による特別賞 『現地消費型ふるさと納税を活用した「四方よし」の取り組み』特別賞】 ◎株式会社旅行読売出版社、読売新聞大阪本社、TOPPAN株式会社、TOPPANデジタル株式会社 株式会社エスツー、株式会社DGフィナンシャルテクノロジー 『現地消費型ふるさと納税を活用した地方鉄道・沿線自治体支援の取り組み 「テツふる」』 (選考理由) 近年、ふるさと納税は、豪華な返礼品に焦点が当たりがちであり、本来の目的である「地域を応援する意識」をどのように育んでいくかが、ひとつの課題となっています。そうした中、「テツふる」の取り組みは、地域経済の活性化に直結する「現地消費型ふるさと納税」の新たな可能性を切り拓いたとして高く評価されます。このプロジェクトの最大の特長は、専用サイトを通じて任意の自治体へ寄付をすると、即座に寄付額の最大30%分のデジタル商品券が発行される点にあります。この商品券は、地方鉄道会社の魅力的な体験プランや、沿線地域の地元店舗での買い物に1円単位で利用できます。 特に注目すべきは、疲弊する地方鉄道と沿線自治体の支援という、喫緊の課題に特化している点です。初期費用やランニングコストが不要で、小規模からの導入も可能なこのシステムは、自治体・鉄道会社・地元店舗・利用者が一体となり、「四方よし」の関係を築き出します。現地で手軽に寄付ができる仕組みは、地域の魅力を直接伝え、新たな交流を生み出す可能性を秘めています。また、沿線自治体から援助を受けるケースが多い地方鉄道が「鉄道があるから人が来る、沿線でお金が使われる」という逆転の発想により、地域経済に大きな活性化をもたらすことが期待されます。ここに『現地消費型ふるさと納税を活用した「四方よし」の取り組み』特別賞を授与します。 |
||
|